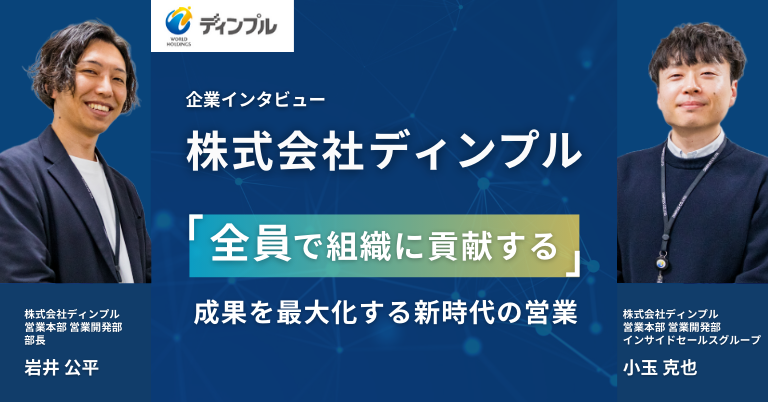今回は、株式会社ディンプルのインサイドセールス部門で活躍するグループ長 岩井様 セールスメンバー 小玉様のお二人にインタビューを実施しました。
人材派遣サービスを展開するインサイドセールス部門の特徴や成果を上げるための取り組み、今後の展望についてお話を伺いました。
営業推進部からの進化と成長
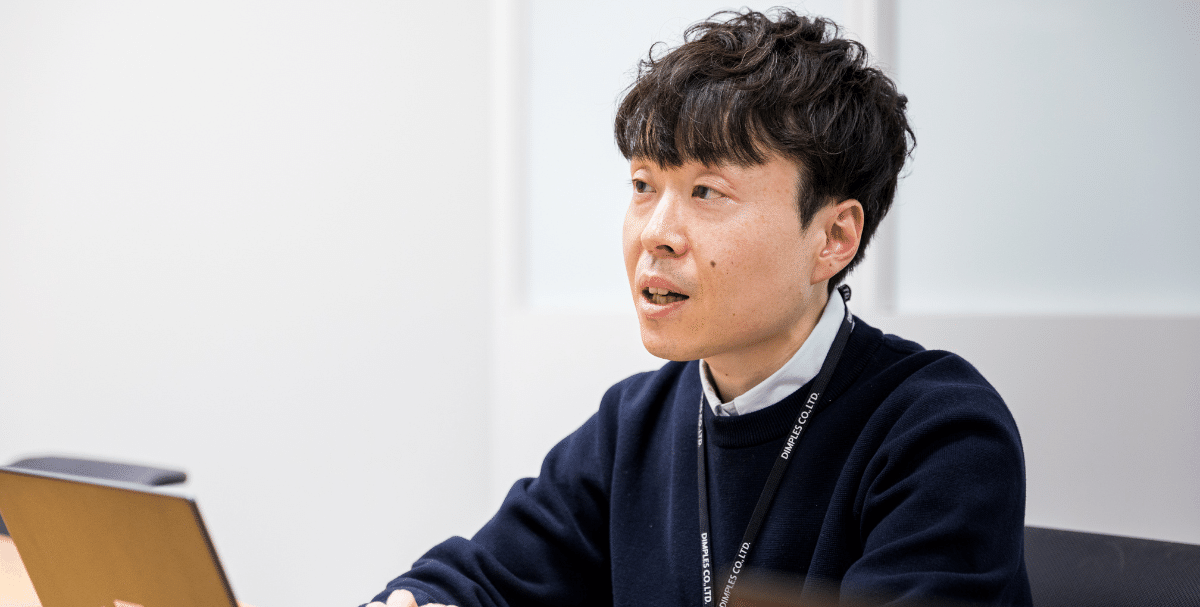
―インサイドセールス立ち上げの背景を教えてください
小玉様:インサイドセールスが部門化したのは、今期からですね。その前身となる営業推進部が設立されたのは、5年ほど前になります。
当時は既存のクライアント対応に追われていて、新規開拓が疎かになっていた部分がありました。それでは会社として成長がないと感じていたので、新規の企業様とコンタクトを取る機会を増やすために営業推進部を設立したんです。
業務内容としては、商談機会の獲得を目標に企業様をリスト化して、テレアポやダイレクトメールでアプローチをしていました。その流れを組んで、インサイドセールス部門が立ち上がったんです。
―インサイドセールスは今でこそ浸透してきた営業手法ですが、当時の社内理解や周囲からの見え方というのはいかがでしたか?
小玉様:発足当時、私はフィールドセールスを担当していたので、インサイドセールスが何をしているのか分からない部分が多かったですね。なので、テレアポをする人達なのだろうなという認識でした。
実際にジョインしてみると、テレアポ以外にも作戦を練ってリストを作成したり自社が保有するサービスの提案内容を考えたり。色々と戦略的にアプローチをしていく必要があるなと実感しました。
社内理解は応援してもらえていると思いますが、まだそこまで業務を認知されていない状況なので発展途上かなと感じてますね。
―インサイドセールスとは何かというところから始まったんですね。発足時から現在に至るまでのメンバー構成を教えていただけますか?
小玉様:営業推進部が発足した時は、5名程度でスタートしてメンバーの異動や産休などで変動があり、昨年は2名で活動してました。
現在は私含め、グループ長の岩井と宮崎県、山形県からリモートワークで1名ずつ在籍していて計4名です。
もともとは、フィールドセールスや営業所で活躍していたメンバーなので、各分野の知見を活かして営業活動を行っているというのが部門の特色になります。
―インサイドセールスのトスアップ先を担当していた方々なんですね。マーケティング部門との連携は、どうされてますか?
小玉様:ホームページからの流入は、インサイドセールス部門で初回対応をします。そこで、案件化できる可能性が高いリードを営業部にトスアップしてますね。
リレーションは、チャットや電話、メールを使用して「こういう企業様とコンタクトが取れたので商談を設定したい」というのを私たちで調整しています。
デジタルツールの導入で営業効率が飛躍的に向上
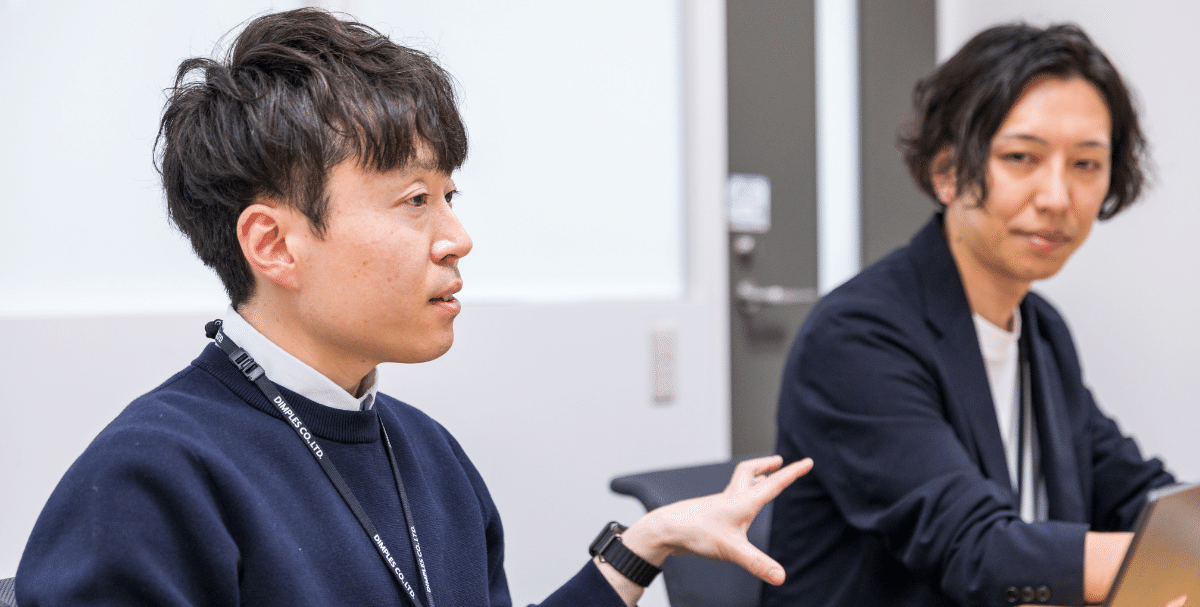
―具体的にはどのような活動をされているのでしょうか?
小玉様:新規開拓の流れは、まず営業部とどういったところを拡大していきたいかを相談します。ここで、新しく開業する商業施設やトレンドの業界など取引先を増やしたい企業をピックアップしていくんです。
それを、インサイドセールス部門で調べてリスト化した後にアプローチをしていきます。
―その営業プロセスの中で上手くいっている施策や事例はありますか?
小玉様:手応えがあったなと思う施策は、ロボットのRPAを活用したリスト化です。
フィールドセールスの時は、求人広告サイトから一つ一つ企業情報を調べてアプローチをしていました。当時はサイトを開いて、たくさんページを遷移させながら作成していたので大変でしたね。
ロボットを使ってからは、300件程のリストを瞬時にスプレッドシートへ抽出できるようになったので、アプローチをする効率が格段に上がりました。実際に、商談を獲得できた企業様も増えましたね。
あとは、昨年新しくフォーム営業のツールを導入してみたんです。ホームページの問い合わせフォームに自動でメールを送付できるのですが、1万社以上に配信することができました。
この作業を手動でやるのは難しいので、商談機会を増やすチャンスを創れたのかなと思っています。ツールの導入は、効率化や省人化、成果に繋がったというところで良かったと感じてますね。
岩井様:受注時は、代表のメールアドレスを作って情報を一元管理しています。以前は、メールのBCCで送られてきたものを、各々の営業所や営業担当者が個別で受けていたんです。
それだと、情報が届いている人といない人に偏りが出てしまっていたので、インサイドセールスで集約して管理するようになりました。
―個人宛だと知らないうちに連絡が途絶えてしまうこともあるので、共通のメールアドレスで管理するのは良い施策ですね。
チームで成果を最大化するインサイドセールスの組織づくり
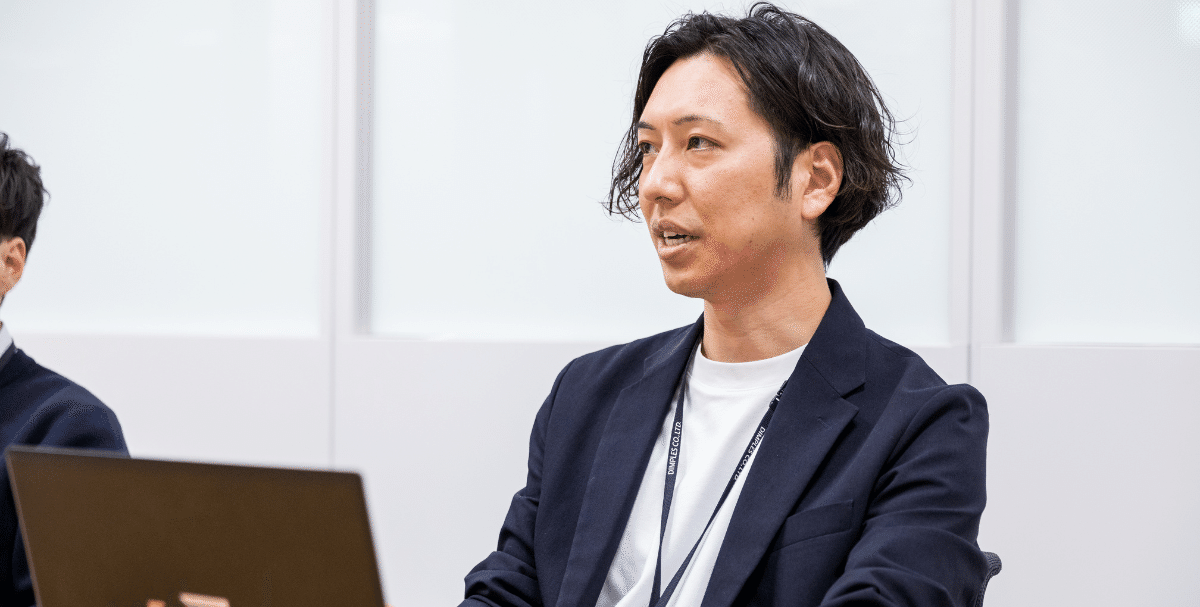
―メンバーマネジメントの取り組みを教えてください
岩井様:管理体制は、自身の売上に着目する個人主義ではなくチームのKPIを統一して「皆で組織に貢献していくこと」です。リモートワークは、各々が独立したKPIで動くと孤立してしまうんですよね。
なので、メンバーのメンタリティの維持や組織貢献、インサイドセールスが初めての方もいるので連携強化といった意味を兼ねてこの体制にしています。
KPIは、インサイドセールスが部門化する前と変遷がありまして。初めは、アポイント獲得数だったんですね。それが受注数に変わり、現在はインサイドセールスを経由して生まれた関与売上をチームの指標にしています。
―メンバー育成においてはいかがでしょうか?
岩井様:まずは、手法を学ぶところから取り組んでますね。一番長くインサイドセールスの業務を経験しているのが小玉さんなので、皆で聞きながら手探りで進めています。
営業は正解がない部分もあると思うので、実践しながら学ぶというのが大きな軸だと感じてますね。
メルマガの業務では「皆さん、チェックをお願いします」といったようにメンバー同士で意見を出し合って作成しています。
営業に理解があるメンバーなので育成というよりかは、全員で作り上げているところが大きいかなと思いますね。
―営業の基本的な知識は習得されているメンバーですもんね。リモートという働き方に対する従業員のエンゲージメントは、いかがでしょうか?
岩井様:リモートワークはコミュニケーションが取りにくいといった声もあるのですが、相談や連絡がしづらいという雰囲気は一切ないです。
これは、小玉さんが毎日電話でメンバーと話をしてくださっているからだなと感じています。
ただ、一緒にご飯を食べながら「こういうことができたら面白いよね」といった対面だからこそできるコミュニケーションの機会をつくる難しさはありますね。電話は、目的がないとかけないので。
小玉様:電話をする時は用件を作ってかけていますが、7割は雑談を交えるようにしています。仕事をしている場所がそれぞれ違うので「寒いですよね」、「雪大丈夫ですか?」といった天気の話をよくしますね。
電話やビデオ通話のコミュニケーションは、どうしても時間を確保しているという感覚が強いじゃないですか。なので、中身のない雑談はしづらいという課題感は感じてますね。
―メンバーの成果不良やモチベーションが低下してしまった場合は、どのようにフォローされてますか?
岩井様:まずは、メンバーと話をして原因を突き止めます。相談に対しては、目に見える形でフィードバックをしてあげるだけでもガス抜きになると思いますよ。
あとは、自身のTODOがどういうプロセスで成果に繋がっているのかという進捗を可視化するのがすごく大事だなと感じています。
そのためにも、関与売上や受注数、アプローチ数などのKPIを作って見えるようにしてます。
小玉様:リモートワークは、モチベーションが低下しているかどうかを気づくのが難しいこともありますよね。個人的に意識しているのは、業務の進捗を見るようにしていて。
仕事の進みやチャットのレスが遅かったりした時は、ダイレクトに聞くと話しづらいと思うので、別の話題を出しながら「大丈夫?」といった声かけをしています。
岩井様:モチベーションは、納得することだと感じていて。業務の目的が分からなくなったり、自分がやりたいこととやらなければいけないことが違ったりすると低下に繋がってしまうんですよね。
ディンプルのインサイドセールス部門は、自由度が高くてルーティン業務を自分たちで決めているんです。
企業の課題に対するアプローチ方法は、電話以外にもメルマガやSEO、資料作成など色々な手法があるので自分の強みを活かしやすいんですよね。
自分のやりたいことができる環境であれば、モチベーションは担保されるかなと思います。それが成果に繋がれば仕事が楽しくて仕方がないと思いますね。
営業プロセスの最前線を担う組織へ
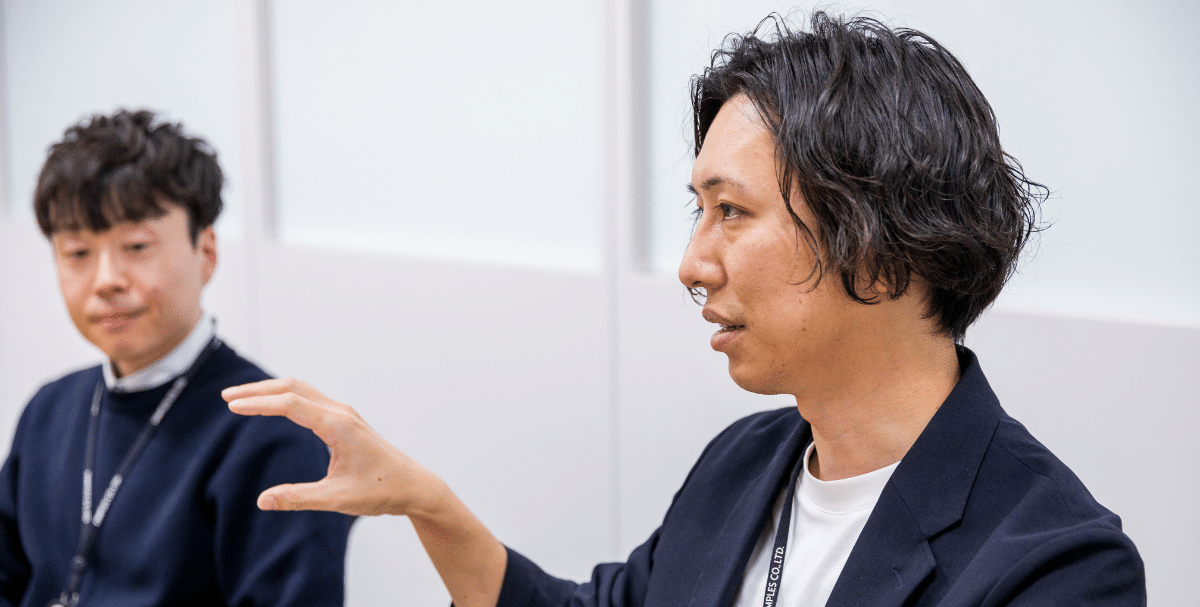
―今後は、インサイドセールス部門をどのように強化していきたいですか?
小玉様:インサイドセールスは、近年ようやく役割やプロセスが社内に浸透してきたのかなと感じていて。
今後は、各拠点長や営業担当者が属人的に行っていた業務を組織間で連携を取って進めることが強化になるのではないかと考えています。
岩井様:やりたいことはたくさんあるのですが、介在価値の可視化が大事だと思ってますね。
例えば、「メルマガで獲得したクライアント様の8割が休眠顧客でした」という分析結果があれば、メルマガが何に貢献しているのかという指標が明確になります。
組織は売上だけではないので、担当している業務にどんな価値があるのかを、私たちが解像度を上げて説明していきたいですね。
―ビジネスにおけるインサイドセールスの役割は、どのように変化していくと思いますか?
小玉様:今後は、会社を先導して引っ張っていく部門になるんだろうなと思います。フィールドセールスは、目の前の業務にフォーカスすることが多くて遠くを見る機会が少ないんですよね。
インサイドセールスは、営業プロセスの全体を見ながら各部門のサポートを推進していく役割があると思うんです。
ただアポイントを取るだけではなく、営業部にリサーチした情報やナレッジを共有する立場ですね。
あとは、こういった体制で戦略を立てたら良いのではないかというアイデア出しもできるようになれたらと考えています。まだ、そういった体制が構築されていない会社も多いのではないかなと感じてますね。
岩井様:私は、SDRとBDRで2つの役割があると思っています。SDRでは、コミュニケーション能力に偏重した営業活動から脱却できることです。
働き方やスキルの多様性を担保できるというのは、インサイドセールスの大きな可能性だと思いますね。
産休から復帰する方や引っ越して会社に来られない方でも、営業活動を続けられる働き方を提供できるかなと。
BDRは、自転車で例えるとギアの重い営業活動を担うのがインサイドセールスの役割だと感じています。フィールドセールスは、短期的に前に進むために漕いだらすぐに進む軽いギアで行かなければいけないと思うんです。
一方で、遠くに行こうと思ったら重いギアで進む必要があるんですよね。大企業の情報を取得できたことも、お金ではない利益や進捗に繋がったりするので。それが、インサイドセールスの位置付けなのかなと思います。
多様な働き方を実現するインサイドセールスの可能性

―インサイドセールスのやりがいや魅力は何ですか?
小玉様:インサイドセールスのやりがいは、企業様の役に立てているなという実感がダイレクトに得られることだと思っています。
フィールドセールスの時は人材派遣部門の担当だったので、提案するサービスがどうしても人材派遣に偏ってしまっていました。
時には企業様のニーズは正社員の採用であるにも関わらず、人材派遣に誘導するようなコミュニケーションを取ることもありました。
当時は「無理に提案してしまったのではないか」「本当に企業様のニーズに応えられているのかな」と思うことも多々ありましたね。
インサイドセールスは、ディンプルが扱っているサービスの全てを紹介できるんです。提案できる商材が多いので、顧客のニーズに添える確率も飛躍的に上がりました。
企業様の役に立てるというのは、やりがいでもあり、一番の面白さに繋がっているかなと感じています。
―ありがとうございます。最後にインサイドセールスに興味を持っている方へメッセージをお願いいたします!
岩井様: 今後インサイドセールスを志す方は、成果の可視化が難しいと感じる局面が必ずあると思います。
持続的に部署を発展させる上で大事なのは、会社の目標にコミットした介在価値を定量的に示すことです。
イメージは、バレーボールのセッター役ですね。例えば、KPIが100本トスを上げることだとします。それを自分が達成できたとしても、アタッカーが打った時に点数にならなければ勝つことはできません。
トスを上げたことに対する満足感ではなく、点数化するために「今のトスはどうでしたか」、「もっと高くした方が打ちやすいですか」と模索する必要があるんです。
会社が目指すゴールを達成するには、成果を数値化してPDCAを回していくことが大事な取り組みだと思います。
小玉様:インサイドセールスが良いなと思うのは、働き方の多様性や適材適所に人材を配置できるところです。営業が苦手な方やマーケティングが得意な方は、メルマガやライティング業務などの間接的な営業手法でも活躍できます。
なので、「企業様の役に立ちたい」といった貢献意識が高い人は、インサイドセールスに向いていると思いますね。
株式会社ディンプル
HP:https://www.dimples.co.jp/
事業内容:人材派遣事業 有料職業紹介事業 業務受託事業 教育研修事業
※本記事で紹介している内容は、2025年3月17日掲載時点の情報に基づいております。サービスの詳細は変更される場合がありますので、提供企業のお問い合わせ窓口にてご確認ください。

IS factory magazine(アイエス ファクトリーマガジン)編集部です。2022年開設。
定期的にインサイドセールスや営業に関するノウハウ、セミナー情報を発信しています。